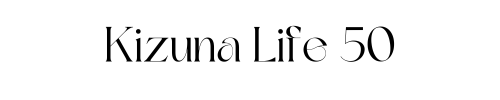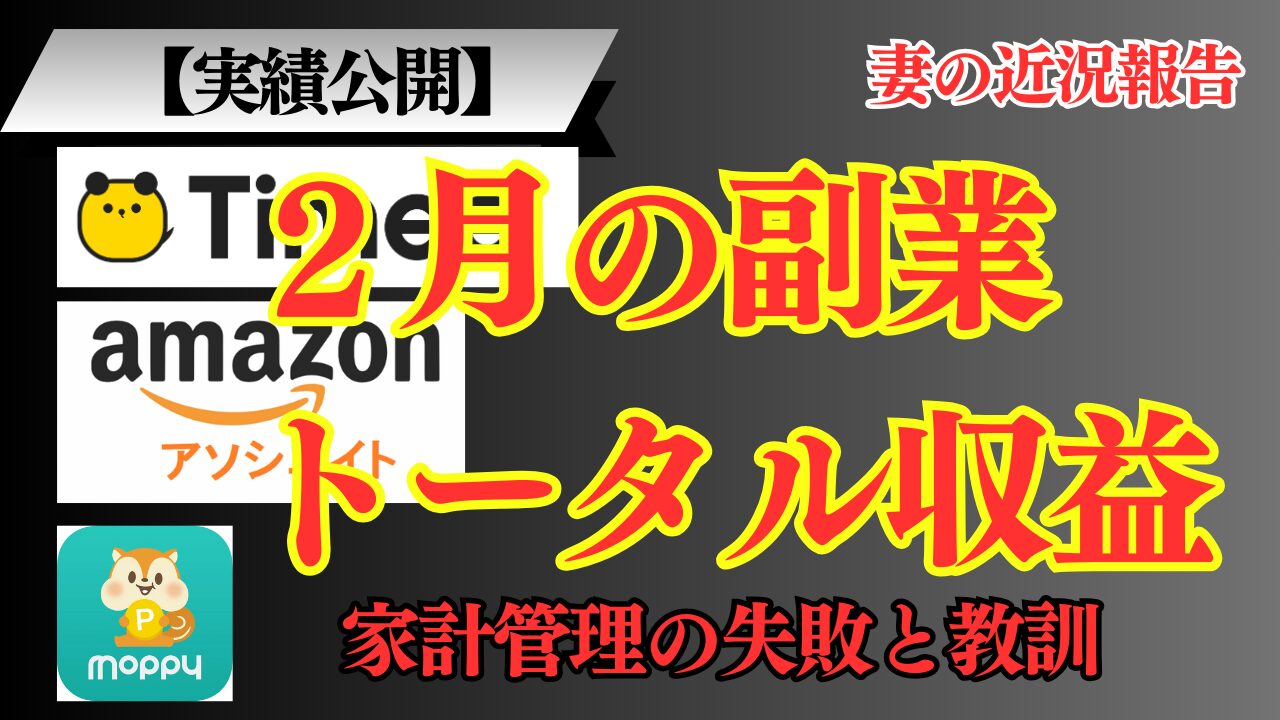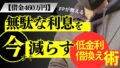はじめに:借金460万円からの再出発
こんにちは、借金460万円の返済に挑戦中のFPヨシローです。
多くの方から「具体的な副業収入の内訳が知りたい」「家計管理はどうしているの?」というご質問をいただいたので、今回は2月の副業収益の詳細と、家計管理の失敗から学んだことをシェアしたいと思います。
この記事では、私が実際に体験している副業の具体的な収益内訳と、家計管理の方法について詳しくお伝えします。特に、タイミー、アマゾンアソシエイト、ポイ活という3つの副業それぞれの特徴と実績、そして臨時出費に直面した際の対処法や家計管理の基本原則についてご紹介します。さらに、家族全員で協力して取り組んでいる「給料日の家計会議」についても詳細にお話しします。借金返済中の方、副業に興味のある方、そして家計管理に悩んでいる方にとって、実践的な情報を提供できればと思います。
2月の副業収入内訳:合計24,043円の実績
2月に取り組んだ3つの副業で合計24,043円の収入を得ることができました。前月比+143円と微増ながらも、着実に前進しています。460万円の借金を考えると、まだまだ小さな額かもしれませんが、こうした小さな積み重ねが大きな変化を生み出すと信じています。
それぞれの副業について詳しく解説します。
1. タイミー:16,400円(早朝仕分け作業)

タイミーは単発バイトマッチングアプリで、空いた時間に手軽に働くことができるサービスです。私は自宅から徒歩5分という立地を活かして、ヤマト運輸の早朝仕分け作業を選びました。
具体的な仕事内容としては、朝5:30から8:30までの3時間、週に1回、土曜日に働いています。主な業務は荷物の仕分けで、比較的単純作業ですが、朝の時間帯は集中力も高く、効率よく作業を進めることができます。
2月は4回出勤し、1回あたり4,100円、合計で16,400円の収入を得ることができました。時給換算すると約1,360円になります。一般的なアルバイトと比べても時給は悪くありませんが、何より大きなメリットは通勤時間がほとんどないことです。自宅から5分で職場に着けるため、往復の通勤時間を含めても3時間10分程度の拘束時間で済みます。
また、土曜日の朝に働くことで、平日の本業への影響がまったくありません。朝早く起きるのは正直大変ですが、慣れてしまえば問題ありません。むしろ、午前中に作業が終わるので、その後の土曜日を有効に使えるという利点もあります。
タイミーでの仕事は、デスクワークが中心の本業とは異なり、体を動かす仕事なので、運動不足の解消にもなっています。また、定期的に働くことで生活リズムも整いやすく、健康面でもプラスの効果を感じています。
タイミーを活用する際のコツとしては、自宅からなるべく近い職場を選ぶこと、継続して同じ仕事を選ぶことで慣れて効率が上がることなどが挙げられます。また、早朝や深夜など、少し大変な時間帯は時給が高めに設定されていることが多いので、自分のライフスタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。
2. Amazonアソシエイト:143円

次に、Amazonアソシエイトでの収益についてお話しします。正直に言いますと、こちらはまだ始めたばかりで苦戦している状況です。2月は、ブログでの商品紹介が1件しか成約に至らず、収入はわずか143円でした。
Amazonアソシエイトは、Amazonの商品を自分のブログやSNSで紹介し、そのリンクから購入があった場合に報酬が発生するアフィリエイトプログラムです。商品カテゴリによって報酬率は異なりますが、一般的に購入金額の1〜10%程度が報酬となります。
現在、私が直面している課題はいくつかあります。まず、コンテンツの量と質が不足しています。アフィリエイトでは、多くの人が訪れるコンテンツを作ることが重要ですが、まだ記事数が少なく、また読者にとって本当に価値のある内容になっているかどうか改善の余地があります。
また、SEO(検索エンジン最適化)対策も不十分です。いくら良い記事を書いても、検索エンジンで上位表示されなければ読者の目に触れる機会が少なくなります。キーワード選定や記事構成など、SEOの基本的なテクニックを学び、実践する必要があります。
さらに、商品選定のノウハウも足りていない状況です。どのような商品を紹介すれば読者の興味を引き、かつ購入につながりやすいのか、まだ手探りの状態です。
しかし、少額でも継続することには大きな意義があると考えています。Amazonアソシエイトは、一度記事を書いておけば、その後も継続して収益が発生する可能性があるパッシブインカム型の副業です。短期的な成果にこだわらず、長期的な視点で取り組んでいくつもりです。
今後の改善策としては、まず特化した商品レビューの充実を図ります。自分自身が実際に使用した商品や、専門知識を活かせる分野の商品に絞ってレビューを書くことで、説得力のあるコンテンツを作成できると考えています。
また、キーワード調査を徹底し、検索されやすいキーワードを記事に取り入れることでSEO対策を強化します。特に「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」といった購買意欲の高いキーワードを狙っていきたいと思います。
Amazonのセール情報を活用した記事作成も効果的です。プライムデーやブラックフライデーなど、大型セール時には購買意欲が高まるため、事前にそうした時期に合わせた記事を用意することで成約率の向上が期待できます。
さらに、読者の悩みを解決する記事の増加も重要です。単に商品を紹介するだけでなく、「〇〇の悩みを解決する方法」といった形で、読者の抱える問題を解決する内容を提供することで、信頼関係を構築し、結果として成約率の向上につなげたいと考えています。
Amazonアソシエイトは、初期段階ではなかなか成果が出にくいものですが、コツコツと継続することで徐々に成果が出てくるものだと理解しています。焦らず着実に進めていきたいと思います。
3. ポイ活:7,500円(証券口座開設)

3つ目の副業は「ポイ活」です。2月は証券口座の開設キャンペーンを利用して、合計7,500円の収益を得ることができました。
ポイ活とは、ポイントサイトを経由して買い物や各種サービスの申し込みをすることで、ポイントを貯めて現金や電子マネーに交換する活動のことです。今回は、証券口座の開設キャンペーンを活用しました。
具体的には、大和コネクト証券の新規口座開設で5,500円、松井証券の新規口座開設で2,000円、合計7,500円のポイントを獲得しました。これらのポイントは、後日現金や電子マネーに交換することができます。
ポイ活の大きなメリットは、申込みにかかる時間が非常に短いことです。証券口座の開設手続きは、各社とも15分程度で完了します。必要なのは身分証明書と銀行口座情報だけなので、準備も簡単です。時間対効果を考えると、非常に効率の良い副業と言えるでしょう。
特に証券口座の開設は、一般的に高額なポイントが付与されることが多いので、ポイ活の中でもおすすめのジャンルです。また、口座を開設しておくことで、将来的に株式投資を始める際にもスムーズに取り組めるという副次的なメリットもあります。
ポイ活で証券口座を開設する際の注意点としては、複数の証券会社を短期間で申し込むと審査に通りにくくなる可能性があることです。そのため、1ヶ月に1〜2社程度に抑えるのが無難です。また、申し込み前にポイントの付与条件をしっかり確認することも重要です。単に口座を開設するだけでなく、入金や取引が条件となっている場合もあります。
今後のポイ活では、証券口座の開設だけでなく、クレジットカードの発行やサブスクリプションサービスの無料トライアルなど、他のジャンルにも挑戦していく予定です。特にポイントサイト経由での株式投資なども検討しており、投資自体のリターンに加えてポイントも獲得できるという一石二鳥の効果を期待しています。
ポイ活は、小さな労力で確実に収益を得られる手段として、今後もさらに活用していきたいと考えています。特に単発で高額ポイントが獲得できるサービスを中心に、効率良く取り組んでいく予定です。
予想外の出費と家計管理の失敗

2月は副業収入を得られた一方で、予想外の出費も発生しました。このような突然の出費が、家計の危機を招くことになったのです。
最も大きかったのは家賃の更新料で、60,000円かかりました。2年ごとの家賃更新は、契約時には頭に入れていたはずなのに、すっかり忘れていたのです。更新のお知らせは届いていたものの、後回しにしていたため、気づいた時には支払期限が迫っていました。
また、住民税の納付も17,000円かかりました。普段は給与からの天引きですが、確定申告で修正があり、追加納付が必要になっていたのです。
これらを合計すると、77,000円もの臨時支出が発生しました。通常の月の支出に加えて、この額が家計を直撃したことで、家計のバランスが大きく崩れてしまいました。
このような状況に陥った原因を振り返ると、根本的な問題は事前の収支計算をしていなかったことにあります。毎月の給料が入ってくるたびに、まずその月の固定費や臨時支出がどれくらいあるのかを確認し、それらに必要な金額を確保した上で、残りを自由に使えるお金として管理するという基本的なことができていなかったのです。
ファイナンシャルプランナーとして他の方々にアドバイスをしながら、自分自身の家計管理がおろそかになっていたという皮肉な状況でした。「医者の不養生」という言葉がありますが、まさにその通りの状態だったのです。
給料が入ると、とりあえず使えるお金があるという安心感から、計画性なく支出していました。また、クレジットカードの利用も多く、実際にどれだけ使っているのかが見えにくくなっていたことも問題でした。
そして、最大の問題は家計の全体像を把握していなかったことです。「今月はいくら使えるのか」「今月はどんな臨時支出があるのか」といった基本的な情報を整理せずに生活していたため、突然の出費に対応できなくなってしまったのです。
これらの経験から、家計管理の重要性を痛感しました。特に借金返済中は、通常以上に綿密な家計管理が必要なのだと改めて認識しました。
家族の支え:奥さんへの感謝

家計管理と借金返済の話をする中で、欠かせないのが家族、特に奥さんの存在です。
私の奥さんは、10年もの間、一人で借金を抱え続けてきました。その間、誰にも相談できず、毎日の生活の中で返済の重圧と向き合い続けていたのです。それでも、家事をこなし、子どもたちの世話をし、私が気づかないように努力し続けてくれていました。
今思えば、毎日の食事の用意、洗濯、掃除、子どもたちの送り迎えなど、日常の細やかな作業をこなしながら、内心では借金の重荷を背負っていたことを思うと、心が痛みます。私自身、家計の管理をほとんど奥さんに任せきりにしていたことで、その負担をさらに重くしていたことに対して、深い反省があります。
今回の臨時支出や家計管理の問題も、本来なら奥さんに頼りきっていた部分です。しかし、借金が明らかになった今、私が積極的に家計を把握し、奥さんの負担を少しでも減らすことが重要だと感じています。
奥さんは現在、少しずつ心の回復に向かっています。精神的な疲労が蓄積していたため、すぐには元の状態に戻れませんが、徐々に笑顔を見せる機会が増えてきました。特に、副業の収入報告をすると、小さな笑顔を見せてくれるようになりました。「そんなに頑張ってくれているんだね」という言葉をかけてくれることもあります。その笑顔と言葉が、私にとって何よりの励みになっています。
家計管理と借金返済は、単なる数字のやりとりではありません。家族の絆や信頼関係、そして心の健康にも深く関わる問題です。これからは、奥さんの心身の回復を最優先にしながら、家族全体で少しずつ借金返済に取り組んでいきたいと思います。
「家族の健康と幸せがあってこその借金返済」という視点を大切にし、バランスを取りながら進めていくことが重要だと感じています。奥さんのペースを尊重し、無理のない範囲で協力し合える関係を築いていきたいと思います。
改善策:「給料日の家計会議」で家計改革

この失敗から学び、3月からは大きく家計管理を変えました。最も重要な改善点は、**給料入金日に行う「家計会議」**の導入です。
給料が入ったその日のうちに、家族で集まって家計の会議を開くことにしました。以前は給料が入ってから、徐々にお金が減っていき、月末になって「あれ?もうこんなに使ったの?」と気づくパターンでしたが、これを根本から変えることにしたのです。
家計会議では、まず固定費の確認と支払い予約を行います。家賃、光熱費、通信費、保険料など、毎月決まって発生する支出を洗い出し、それぞれの引き落とし日と金額を家計簿に記入します。これにより、「いつ、いくら必要か」が明確になります。
私たちの場合、家賃が8万円、光熱費が平均1.5万円、通信費が1.2万円、保険料が1.8万円などと、固定費だけでもかなりの金額になります。これらを優先的に確保することで、後から「支払いに足りない!」という事態を防げるようになりました。
次に、その月特有の臨時支出の洗い出しを行います。子どもの学校行事にかかる費用、季節の衣類購入、車検や保険の更新など、定期的ではないけれど必要な支出を予め把握します。
例えば、3月は子どもの新学期準備で約3万円、車の点検で1.5万円などの臨時支出がありました。これらを前もって把握しておくことで、突然の出費に慌てることなく対応できるようになりました。
カレンダーに大きな支出の予定日をマークしておくことも効果的です。視覚的に「いつ、どんな支出があるか」が分かるため、心の準備もできますし、忘れることも少なくなります。特に年に1回のような支出こそ、忘れがちなので注意が必要です。
3つ目に、借金返済への充当額を確定します。毎月の最低返済額に加え、可能であれば追加で返済できる金額を決めます。高金利のものから優先的に返済することで、効率的に借金を減らしていけます。
私たちの場合、毎月の最低返済額が合計10万円程度あります。これに加えて、副業収入などから可能な限り追加で返済に充てるようにしています。たとえ1万円でも追加で返済できれば、長い目で見れば大きな差になります。
最後に、残額から日々の生活費を算出します。ここでようやく「自由に使えるお金」が明確になります。食費、交通費、日用品など、変動する支出の予算を決め、それを超えないように意識して生活することが大切です。
我が家の場合、食費は月4万円、交通費は1.5万円、日用品は1万円程度と設定しています。これらの予算内に収めるよう心がけることで、月末に「お金が足りない」という事態を防いでいます。
この家計会議の効果は絶大でした。まず、家族全員が家計の状況を理解できるようになりました。特に子どもたちも、お金には限りがあることを実感するようになり、無駄遣いが減りました。長男は「これは必要?」と自分から考えるようになり、次男は貯金を始めました。
また、支出に優先順位をつけることで、何を大切にするかという家族の価値観も共有できるようになりました。例えば、私たちの場合は「子どもの教育費」と「家族の健康」を最優先にすることを確認し合いました。
さらに、「見える化」により、実際にいくら使っているかが明確になったことで、無駄な支出が自然と減りました。「思ったより外食費が多い」「サブスクリプションサービスがこんなにあったのか」など、気づきがたくさんありました。
支出には優先順位をつけることが重要です。私たちの場合、最優先は住居費・光熱費・食費などの生活必需品です。これらは生きていく上で絶対に必要なものなので、最優先で確保します。次点は子どもの教育費・保険料・通信費など、将来のための投資や社会生活を送る上で重要なものです。
その次が借金返済です。これは優先度が高いものの、生活必需品や子どもの教育よりは後回しにせざるを得ません。最後が娯楽費・外食・衣類など、なくても生きていけるけれど、生活の質を高めるためのものです。これらは、余裕がある場合にのみ支出するようにしています。
臨時支出の事前予測方法としては、年間カレンダーを活用しています。1月から12月まで、予想される大きな支出をマークしておくことで、突然の出費に慌てることがなくなりました。
例えば、1月は自動車税、4月は子どもの新学期準備、6月は夏のボーナスから保険料の一括払い、8月は夏休みの家族旅行、12月は年末調整など、それぞれの月に特有の支出があります。特に家賃更新、保険料の年払い、子どもの進学費用など、年に1回しかないものこそ忘れがちなので、カレンダーに記入しておくことが重要です。
さらに、「貯蓄と緊急資金の確保」も計画に入れています。目標は、最低でも生活費3ヶ月分(約60万円)の緊急資金を作ることです。
現在の借金返済中はなかなか難しいですが、月に1万円でも積み立てを始め、少しずつ緊急資金を作っていきたいと考えています。今回のような予想外の出費があっても、緊急資金があれば慌てることなく対応できますし、何より精神的な安心感が違います。
家計会議は一見面倒に思えるかもしれませんが、実際に始めてみると、家計の見通しが立つようになり、精神的な余裕も生まれます。また、家族全員が協力して家計を管理することで、お金に対する意識も高まります。「使うためのお金」から「管理するお金」への意識の転換が、借金返済の大きな力になると感じています。
まとめ:家計管理の5つのポイント

今回の経験から学んだことを、家計管理の5つのポイントとしてまとめたいと思います。
まず第一のポイントは、収入は入ってからではなく、入る前に計画を立てることです。給料日に家計会議を開き、その月の支出計画を立てることで、計画的な家計管理が可能になります。
多くの人は給料が入ってから「さあ、いくら使おうか」と考えがちですが、そうではなく「給料が入る前に、いくら使えるかを決めておく」という発想の転換が重要です。例えば、月給30万円の場合、固定費15万円、臨時費5万円、借金返済5万円を先に確保し、残りの5万円を自由に使えるお金として管理するといった具合です。
この方法の良いところは、月末に「お金が足りない」という事態を防げることです。計画的に使うことで、無駄遣いも減り、結果的に家計にゆとりが生まれます。
第二のポイントは、固定費と臨時支出を事前に把握することです。年間カレンダーで大きな支出を可視化し、忘れがちな年1回の支出にも注意を払います。
固定費は毎月決まって発生する支出なので比較的把握しやすいですが、臨時支出は予測が難しいものです。そこで役立つのが年間カレンダーです。1月から12月まで、予想される大きな支出をマークしておくことで、「忘れていた!」という事態を防げます。
また、過去の家計簿を見返すことも効果的です。「去年のこの時期にはどんな支出があったか」を確認することで、今年も同様の支出が発生する可能性が高いものを予測できます。
第三のポイントは、家族全員で家計を共有し、協力し合うことです。家族全員が収支状況を理解し、一人に任せきりにしないことで、家計管理の負担を分散できます。
家計管理は、往々にして家族の中の一人(多くの場合は妻)に任せきりになりがちです。しかし、それでは負担が偏り、また他の家族メンバーの協力も得られにくくなります。家族全員が家計の状況を理解し、それぞれができることで協力することが重要です。
例えば、我が家では家計会議に子どもたちも参加してもらっています。小さな子どもでも「今月はお金が少し足りないから、外食は控えよう」といった会話に参加することで、お金に対する理解が深まります。
第四のポイントは、予想外の出費に備え、緊急資金を用意することです。小額からでも積立を始め、最終的には生活費3ヶ月分を目標にします。
突然の出費(車の修理や医療費など)があっても慌てないためには、緊急資金の存在が重要です。理想的には生活費の3ヶ月分(我が家の場合は約60万円)を確保しておくと安心ですが、まずは1万円、10万円と小さな目標から始めることが大切です。
借金返済中は貯蓄よりも返済を優先すべきという考え方もありますが、全くの無貯蓄状態では、予想外の出費があった際に新たな借金をすることになりかねません。少額でも緊急資金を用意しておくことで、そのリスクを減らすことができます。
第五のポイントは、「見える化」で現状を正確に把握することです。収支を書き出して「見える化」し、月末の振り返りで調整することで、より効果的な家計管理が可能になります。
「見えないものは管理できない」という言葉がありますが、家計管理においても同じことが言えます。収支を書き出して「見える化」することで、はじめて現状を正確に把握し、改善点を見つけることができます。我が家では、シンプルなエクセルの表で収支を管理しています。特別なアプリや複雑なシステムは必要ありません。大切なのは継続することです。
月末には必ず振り返りの時間を設け、「予算内に収まったか」「想定外の支出はなかったか」を確認します。この振り返りが次月の計画に活かされ、少しずつ家計管理のスキルが向上していきます。